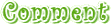ここは齢200歳を超えるもののけの「Ki-Tsu-Ne」が、世界にむけて有ること無いことを発信するサイトです。
おひまなら見てよね
カレンダー
最新トラックバック
最新コメント
[03/15 マナサビイ]
[09/03 Ki-Tsu-Ne]
[09/03 白くじら]
[08/24 Ki-Tsu-Ne]
[08/24 マナサビイ]
Ki-Tsu-Neのリンク集
=====Palm=====
======映画======
======その他======
最新記事
(12/19)
(04/17)
(04/07)
(03/07)
(01/17)
(01/07)
(08/09)
(07/12)
(07/08)
(06/07)
(12/22)
(09/12)
(08/11)
(07/25)
(07/17)
プロフィール
HN:
Ki-Tsu-Ne
HP:
性別:
非公開
自己紹介:
ここは齢200を越えるもののけ「Ki-Tsu-Ne」が、とある山にある小さな祠から世界に向けてあること無いことを発信する場所です。
このサイトへのリンクはフリーです。というか、バンバン張ってちょうだい!!
このサイトへのリンクはフリーです。というか、バンバン張ってちょうだい!!
拍手ください
アーカイブ
カウンタ
広告
2025.12.03
[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
2007.07.01
ハリーポッター 不死鳥の騎士団
ハリーポッターの映画シリーズも5作目になりました。
1作目当時は10歳だった主役の「ダニエル・ラドクリフ」君も今では18歳。最近では劇舞台でヌードになり、賛否両論が出た事が記憶に新しい所です。Ki-Tsu-Neが思うには、彼はまだ18歳だし、レーニン役者じゃあるまいし、いつまでも「ハリー」でいる訳にはいかないのだから、こういう新しい挑戦もいいのじゃないのでしょうか。いきなりヌードには驚かされましたが。それよりもロン役の「ルパート・グリント」君が実年齢以上におっさん臭くなっていたのが気になりました。
今回は1作目・2作目あたりとは違い、大がかりなSFXはあまり見られません。原作シリーズが、最初はファンタジー部分が強く描かれていたのと比べ、巻が進むにつれて、ハリーの心理描写が増えていくのと歩調を合わせているのかもしれません。5巻はまだ1/4しか読んでいないのであまりエラそうな事は言えませんが(映画を観る前に原作を読んでしまうつもりだったのに情けない)。
あと、この話に出てくる新しい先生「アンブリッジ」を見て、私の知人から聞いたO先生(仮名)の話をふと思い出しました。
私の知人が小学校高学年の頃、O先生(女性・推定40代)は彼の音楽の担任でした。彼のクラスはどちらかと言うと授業中でも全く落ち着きが無く騒がしいわんぱくで逞しい子が多く集まっていました。そして、その頃授業の課題として「京の大仏」という童歌を習っていたそうです。この歌は、寛政年間に京都の方広寺にあった大仏が落雷で消失した事を歌にしたものだと言われています。童歌は、その頃起こった事件や、時には政治批判等が題材にされる事が有ります。大っぴらに権力への抵抗を行う訳にはいかなかった時代では、世の中への不満を童歌に託し、所詮子供の「戯れ言」という事を建て前にしながら社会批判が行われた場合も有りました。もっとも、わんぱく少年達にはそんな事は関係有りませんが・・・。
ある日、授業開始時にO先生が「京の大仏」と言うべき所を「奈良の大仏」と間違えてしまったのです。落ち着きのない坊主共わんぱく盛りの子供達はそれを聞くと、大きな声で笑い、そしてはやし立てました。O先生は、そんな子供達に対して一喝。「だまりなさいっ!」そして、O先生の特別講義(説教とも言う)が40分間行われました。
講義の内容について、私の知人は「退屈で眠たかった」と言っています。彼のコメントからすると、O先生の特別講義は知的好奇心を全くくすぐられなかったものだと思われます。
その頃、知人のクラスの担任は、音楽室の下の階にある職員室で休憩を取っていたそうです。いつもなら、上の部屋から自分の児童たちの調子はずれで頭の悪くなりそうな美しい歌声が聞こえてくるはずなのに、その日に限っては静まり返っていました。この頃はそんな時代だったのでしょうか?彼は体罰を多く行う所謂暴力教師だったのですが、さすがにこの特別講義が行われた事に関しては一言「おまえたち、気の毒だったな」との慰めの言葉を頂いたそうです。
世の中との関わり方に悩みをもち始めたハリー少年の活躍をお楽しみ下さい。
ハリーポッター 不死鳥の騎士団 (洋画・ファンタジー)
1作目当時は10歳だった主役の「ダニエル・ラドクリフ」君も今では18歳。最近では劇舞台でヌードになり、賛否両論が出た事が記憶に新しい所です。Ki-Tsu-Neが思うには、彼はまだ18歳だし、レーニン役者じゃあるまいし、いつまでも「ハリー」でいる訳にはいかないのだから、こういう新しい挑戦もいいのじゃないのでしょうか。いきなりヌードには驚かされましたが。それよりもロン役の「ルパート・グリント」君が実年齢以上におっさん臭くなっていたのが気になりました。
今回は1作目・2作目あたりとは違い、大がかりなSFXはあまり見られません。原作シリーズが、最初はファンタジー部分が強く描かれていたのと比べ、巻が進むにつれて、ハリーの心理描写が増えていくのと歩調を合わせているのかもしれません。5巻はまだ1/4しか読んでいないのであまりエラそうな事は言えませんが(映画を観る前に原作を読んでしまうつもりだったのに情けない)。
あと、この話に出てくる新しい先生「アンブリッジ」を見て、私の知人から聞いたO先生(仮名)の話をふと思い出しました。
私の知人が小学校高学年の頃、O先生(女性・推定40代)は彼の音楽の担任でした。彼のクラスはどちらかと言うと授業中でも
ある日、授業開始時にO先生が「京の大仏」と言うべき所を「奈良の大仏」と間違えてしまったのです。
講義の内容について、私の知人は「退屈で眠たかった」と言っています。彼のコメントからすると、O先生の特別講義は知的好奇心を全くくすぐられなかったものだと思われます。
その頃、知人のクラスの担任は、音楽室の下の階にある職員室で休憩を取っていたそうです。いつもなら、上の部屋から自分の児童たちの
世の中との関わり方に悩みをもち始めたハリー少年の活躍をお楽しみ下さい。
ハリーポッター 不死鳥の騎士団 (洋画・ファンタジー)
PR

 管理画面
管理画面